要約
日本では糖尿病の病名見直しが進められている。糖尿病は従来は生活習慣や肥満と結びつけられ、「自己責任」の視点が強調されてきたが、発症には遺伝や環境、社会的要因も関与する。病名の変更は、病の本質に沿った理解を促し、偏見の是正に寄与する第一歩となる。
また映画作品では、糖尿病が社会構造や生活環境と密接に関連することを描き、偏見の解消や医療理解の促進に役立っている。歴史的にも、糖尿病は平安時代から生活習慣と結びつけられ、治療の未発達や合併症の多さと相まって「管理が難しい病気」というイメージが定着し、現代に至るまで社会的スティグマが根強く残っている。
記事のポイント
- 日本では「糖尿病」という名称の、病名の見直しが進められている。
- 糖尿病の発症には遺伝・環境・社会的要因が複雑に絡み合う。
- 歴史的に治療が不十分であったことや生活習慣病のイメージにより、患者への社会的スティグマは現代まで根強く残っている。
Summary
Japan is advancing a review of diabetes nomenclature. While diabetes has traditionally been linked to lifestyle habits and obesity, emphasizing a “personal responsibility” perspective, its onset also involves genetic, environmental, and social factors. Changing the disease name is a first step toward promoting understanding aligned with the disease’s essence and helping correct prejudice.
Additionally, films depict how diabetes is closely intertwined with social structures and living environments, helping to eliminate prejudice and promote medical understanding. Historically, diabetes has been linked to lifestyle habits since the Heian period. Combined with underdeveloped treatments and numerous complications, this led to the entrenched perception of it as a “difficult disease to manage.” This social stigma remains deeply ingrained even today.
Translated with DeepL.com (free version)
日本において、糖尿病についての病名の見直しが始まっている。従来、「糖」を強調してきた日本語の「糖尿病」という病名を、世界的に使われる「ダイアベティス」に近づける議論が進められている。
実際、糖尿病については病名がもたらす誤解や偏見があった経緯があり、社会全体での理解改善が必要とされている。病名そのものが患者の受け止め方や、社会のまなざしに影響することを踏まえると、見直しは単なる用語変更にとどまらず、これからの医療と社会の接点を問い直す重要な契機ともなり得る。
糖尿病はしばしば「生活習慣の結果」であり、「肥満や怠惰と結びついた病気」として誤解されてきた。しかしながら、発症要因には遺伝的素因や生活環境、さらには社会的要因までが複雑に絡み合っている。
また、近年ではマーティン・スコセッシ監督の映画「キラー・オブ・ザ・フラワー・ムーン」や、現在公開中の映画「国宝」といった作品の中でも、糖尿病について、社会的な視線によってどのように語られてきたかが触れられており、少なからず話題となった。
病名の言い換えは、まずは第一歩として有効だ。問題を特定の食品や行動に結びつけず、病の本質に沿った呼称を用いることで、「自己責任」偏重の視点が修正されることは喜ばしい。
Amazon(PR)→
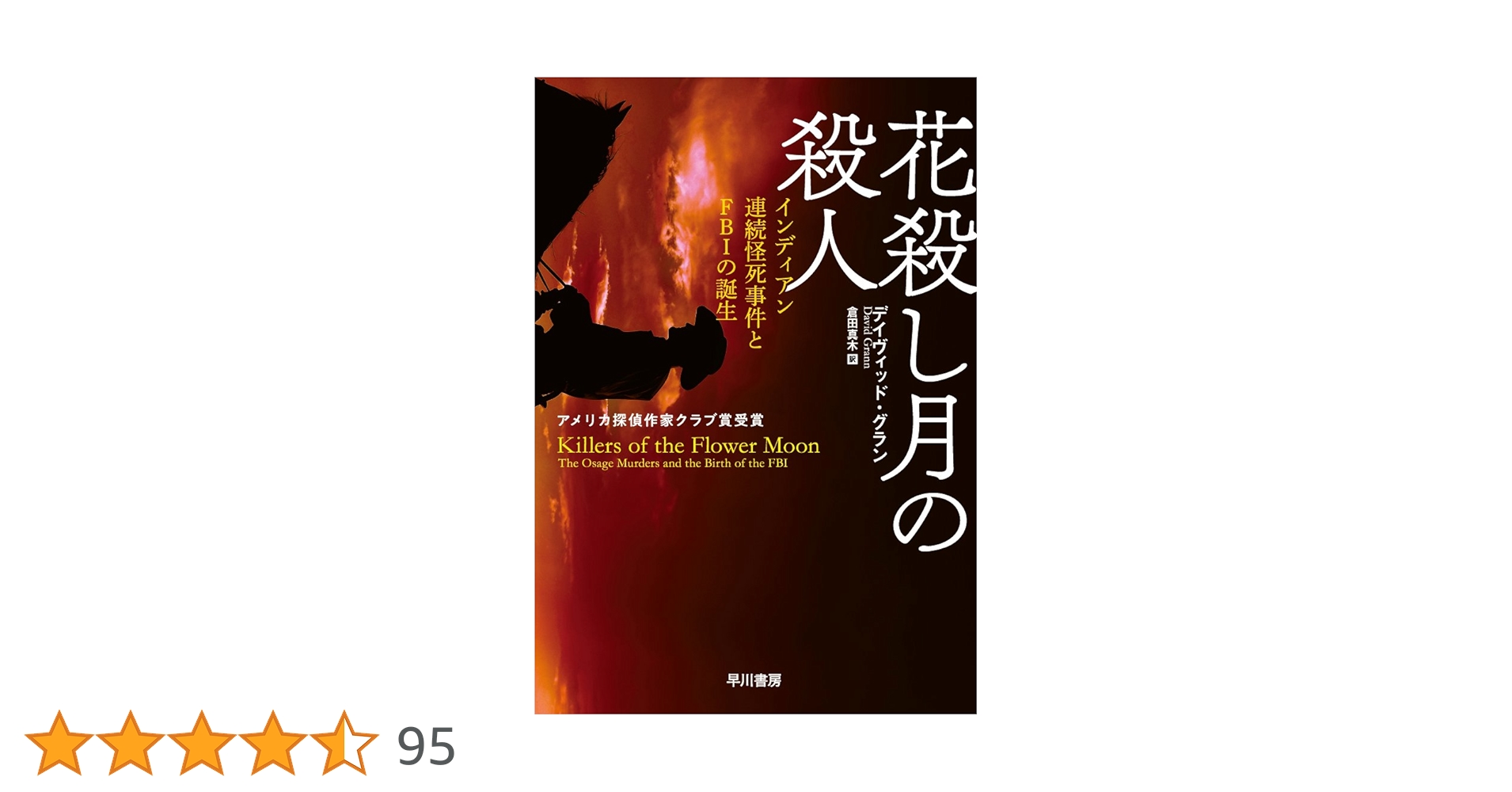
「糖尿病」という名称、偏見の温床に?歴史と現代の課題
「糖尿病」という呼称は、文字通り「尿に糖が出る病気」を意味するが、患者の多くは尿に糖が出ない場合もあり、さらに「不潔」「怠惰」といった偏見やスティグマを生みやすい問題が指摘されていた。


