OpenClipart-VectorsによるPixabayからの画像
要約
2026年のWBC日本独占配信権をNetflixが獲得したことは、日本のスポーツ放送体制の構造的限界を露呈させた。従来の日本の放送モデルは、新聞社・電通・民放による広告収益依存型であり、放映権料を広告で回収する仕組みに依存してきた。しかし、地上波広告費は減少の一途をたどり、制作費は高止まり、国際的な放映権競争に対応できない。
さらに、伝統的に日本のテレビ局はニュースやスポーツに限らず、基本的に自社制作で完結させる“系列内閉鎖モデル”を続けてきた。これにより外部スタジオや独立制作会社との市場取引が育たず、国際水準の制作効率や収益構造が形成されなかった。一方、アメリカでは放送局は外部から番組を購入する「プラットフォーム型」へ移行している。
その結果、日本のプロスポーツは資金循環が乏しく、選手年俸も国際水準に届かない。また、そもそも日本のスポーツは依然として「私有財」として扱われおり、英国のように公共的アクセスを保障する制度は不適切だ。
記事のポイント
- Netflixが2026年WBCの日本独占配信権を獲得したことで、広告依存の地上波モデルが崩壊し、日本の放送産業の構造的限界が露呈した。
- 自社制作主義と系列構造による日本型テレビ局システムのもと、国際競争力を持つ制作・資金循環モデルを築けなかったことが放映権喪失の根本要因。
- 日本のスポーツはそもそも、公共性の欠如と私企業依存の文化構造がある。
Summary
Netflix’s acquisition of exclusive streaming rights for the 2026 World Baseball Classic in Japan exposed the structural limitations of Japan’s sports broadcasting system. The traditional Japanese broadcasting model has relied on advertising revenue generated by newspapers, Dentsu, and commercial broadcasters, depending on a system where broadcast rights fees are recouped through advertising. However, terrestrial advertising revenue continues to decline, production costs remain high, and the system cannot compete in the international broadcast rights market.
Furthermore, Japanese TV stations have traditionally maintained a “closed network model,” producing content entirely in-house, not just for news and sports. This has stifled market transactions with external studios and independent production companies, preventing the development of internationally competitive production efficiencies and revenue structures. In contrast, American broadcasters have transitioned to a “platform model” where they purchase programming externally.
As a result, Japan’s professional sports suffer from poor capital circulation, and player salaries fall short of international standards. Moreover, Japanese sports are still fundamentally treated as “private property,” making systems like the UK’s, which guarantee public access, inappropriate.
Translated with DeepL.com (free version)
2026年のWBCの日本国内独占配信権をネットフリックスが獲得したことは1、日本のスポーツ放送市場における従来の支配構造を揺るがす大きな転換点となる。
長らく、日本のプロスポーツ、とりわけ野球の放映権は読売新聞社系列や電通など広告代理店を軸に、テレビ局が広告枠を販売し地上波で無料放送を提供する仕組みによって成立してきた。ただ、このモデルはコンテンツのマス向け普及に寄与した一方で、広告収益に依存する脆弱さを抱えていたことに留意する必要がある2。
今回、ネットフリックスが代理店や放送局を介さず直接契約を選んだことは今後、オリンピックを含む他の国際大会にも波及する可能性がある3。
注目すべきは、その放映権料である。ネットフリックスが提示したとされる約150億円は、日本市場の常識を大きく超える金額だが、世界的には妥当な金額だ。要は、単に地上波の広告収益モデルだけでは到底回収できないということを示している。
ただ、このことは日本のスポーツビジネスに深刻な課題を突きつける。グローバル市場では「放映権料が下がらない」ことが常態化しており、広告依存の国内モデルでは資金循環が縮小せざるを得ない。
結果、国内選手への高額契約が難しくなり、日本人スター選手の海外流出が恒久化するリスクが高まっていることを示唆する4。
Amazon(PR)→
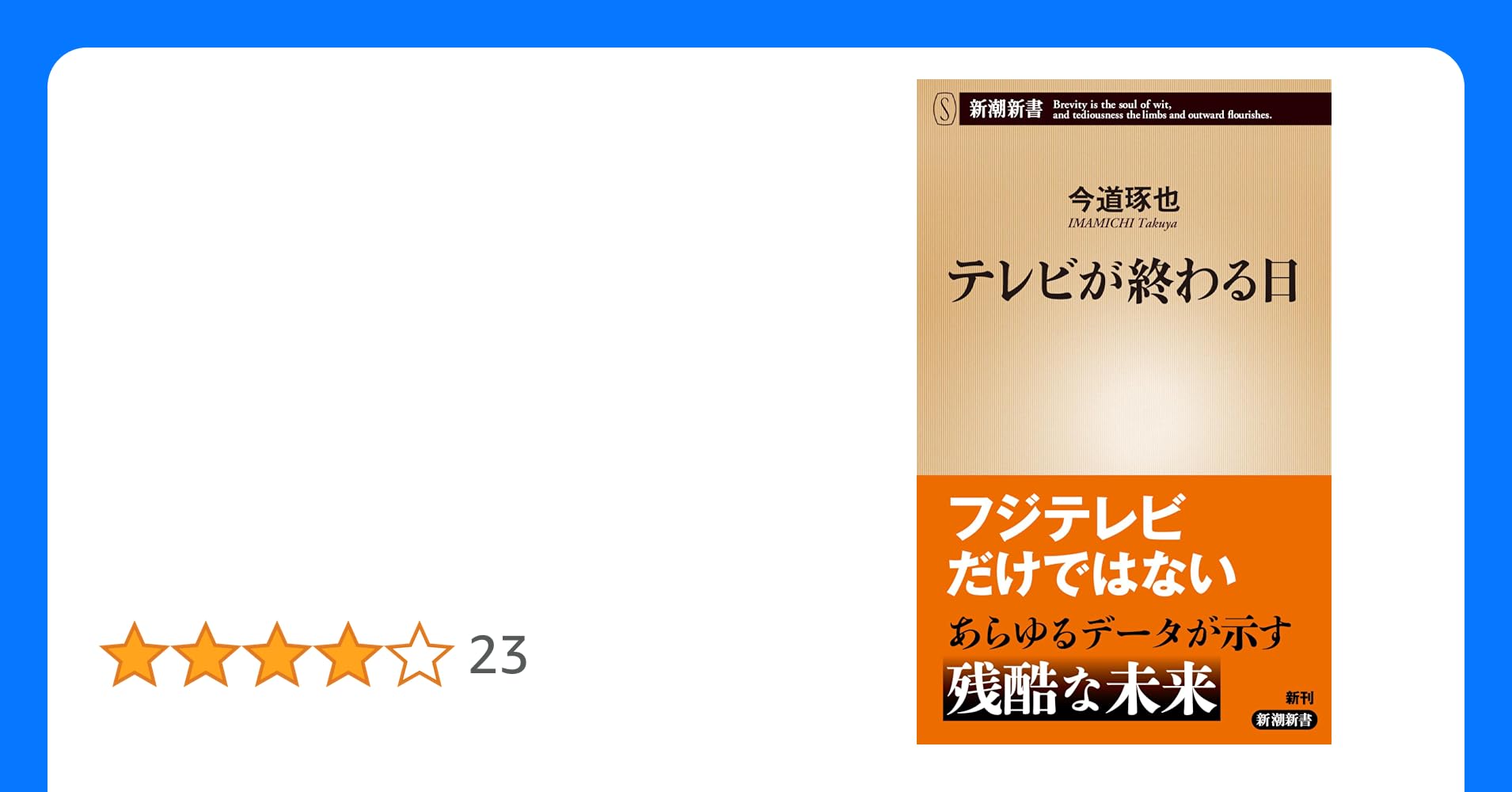
スポーツ放映権、世界で高騰 地上波依存がプロ選手「低年俸」の原因に
いまやグローバルなスポーツ市場の現場では、YouTube、Netflix、Amazon Prime VideoなどOTT事業者による新しい巨大企業の参入による競争激化を背景に、放映権料が構造的に高騰している5。


